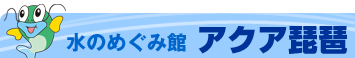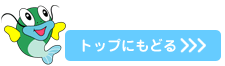~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
アクア琵琶からのメールニュース vol. 20 (2001.8.27発行)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■ 目 次 ■■
[アクア琵琶ニュース] <台風一過> 台風11号の功罪
[Topics] 水草が食べ尽くされた大沢池でソウギョ捕獲作戦
[Last 2 Week] 最近2週間の琵琶湖の水位/瀬田川洗堰の放流量
[休館日のお知らせ] 8月下旬 9月上旬の休館日について
[ビワズコラム] ブルーギルとイケチョウガイの皮肉な関係
┏━━━━━━━━━┓
┃アクア琵琶ニュース┃ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
┗━━━━━━━━━┛
◆<台風一過> 台風11号の功罪 (2001.8.23発信)
台風11号は、21日夕刻に紀伊半島へ上陸し、ゆっくり日本を縦断して23日
に北海道へ再び上陸する予報となっています。この台風により、陸海空の交
通網に大きな影響をもたらしました。台風のもたらす大雨で落石、土砂崩れ
が発生し、交通網が寸断されたり、床上床下浸水被害が各所で発生しました。
被害にあわれた方々にはお見舞い申し上げます。一方、渇水で取水制限を実
施していた一庫ダムでは取水制限を全面解除、日吉ダムでは貯水率は80.3%
となり予定していた流量制限は回避される見通しとなった。
(8/21京都新聞、読売新聞より)
また、琵琶湖においては、降り始めからの流域平均の総雨量が170mmとなり、
-57cmの琵琶湖の水位は43cm回復し、-14cm(23日9時)になりました。
(琵琶湖工事事務所資料より)
ちなみに、単純計算しますと、約2億9千万m3の流入となります。この量は
天ヶ瀬ダム総貯水量の11倍、また大阪ドーム約240杯分に相当します。このよ
うに、渇水状況であったダム湖、貯水湖や植物等生態系には恵みの雨だった
ようです。
┏━━━━━━━━━┓
┃ Topics ┃ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
┗━━━━━━━━━┛
◆水草が食べ尽くされた 大沢池でソウギョ捕獲作戦
平安時代から月の名所として知られる大覚寺境内(京都市右京区嵯峨)の
大沢池(おおさわのいけ)に、スイレンやハスの彩り豊かな景観を取り戻そ
うと学者たちが計画を進めています。池は30年ほど前、水草の過度の繁殖を
防ぐために外来種のソウギョを移入。しかし、水草がすべて食べつくされ、
悪影響が出てきました。計画では、ソウギョの行動を調べて数を管理、水草
の植栽に取りかかろうというものです。 大沢池はかつて、池の3分の1まで
水草が繁殖していましたが、秋の「観月の夕べ」で月が水面に映りにくいた
め、大覚寺や宗門校である京都嵯峨芸術大(右京区)の学生が水草の除去と
池底の泥抜きを行っていました。しかし、労働力の確保が難しくなり、30年
ほど前、ソウギョを大沢池に放しました。 すると水草は3、4年で食べ尽く
され、富栄養化による水質悪化も進み、周辺の湿度も増加し、樹木にコケが
つくなど影響が出てきました。 このため、同大学の真板昭夫教授(観光エコ
ツーリズム専攻)が、造園計画の研究家や釣り師のグループに呼びかけて
「草魚バスターズ実行委員会」(約60人)をつくり、池の景観修復に取り組
むことになりました。
事前調査では、池に生息しているソウギョは30〜40匹と見られる。計画は
3年がかりで、まずソウギョの行動を把握するため3匹を釣り上げ、発信器を
つけて放流する。生態を調べた上で捕獲し、水草の植栽を進める。
真板教授は「京都では美しい自然景観が人とのかかわりの中ではぐくまれ
た。手伝ってくれる50人ほどの学生たちに、景観保護の大切さを伝えていき
たい」と話しています。
▽ソウギョ 中国原産。1メートル以上に成長するコイ科の大型淡水魚。
主に水生植物や藻類を食べる。日本には1943〜45年に利根川水系に持ち込ま
れ、繁殖が始まったとされる。
[京都新聞 2001年8月15日]
┏━━━━━━━━━┓
┃ Last 2 Week ┃ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
┗━━━━━━━━━┛
◆最近2週間の琵琶湖の水位/瀬田川洗堰の放流量
8月
14日(火曜) -46/54
15日(水曜) -48/54
16日(木曜) -49/54
17日(金曜) -51/54
18日(土曜) -53/52
19日(日曜) -54/52
20日(月曜) -56/52
21日(火曜) -57/55
22日(水曜) -35/35
23日(木曜) -16/35
24日(金曜) -13/150
25日(土曜) -13/150
26日(日曜) -14/150
27日(月曜) -16/150
単位:水位(cm)、放流量(m3/sec)
┏━━━━━━━━━┓
┃ 休館日のお知らせ ┃ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
┗━━━━━━━━━┛
休館日
8月28日(火) 9月4日(火)
┏━━━━━━━━━┓
┃ ビワズコラム ┃ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
┗━━━━━━━━━┛
◆ブルーギルとイケチョウガイの皮肉な関係
「びわパール」と呼ばれて親しまれてきた琵琶湖の淡水真珠は、琵琶湖の
固有種イケチョウガイを母貝にした養殖に成功してからはじまりました。
しかし、昭和50年頃には最盛期を迎えた淡水真珠の養殖は、その後生産高が
落ちていきます。その原因がイケチョウガイの減少にありました。琵琶湖の
淡水真珠の養殖に適しているイケチョウガイがうまく育たなくなってしまっ
たのです。
これは養殖の場となる内湖の水質が悪化したためと言われています。この
イケチョウガイと、最近ニュースなどで良く耳にする魚ブルーギルにどのよ
うな関係があるのでしょうか。
ブルーギルは昭和35年頃に日本にやってきました。
その後飼育された稚魚が滋賀県水産試験所にやってきたのです。当時、淡
水真珠の養殖は滋賀県水産業を支える重要な柱でした。そのため真珠の養殖
に用いるイケチョウガイの人工養殖に関する様々な研究が行われていました。
イケチョウガイの幼生は魚のエラやヒレに寄生します。その寄生に最も適
した魚とされたのがブルーギルだったのです。この時実験に使われた西の湖
と呼ばれる内湖から、琵琶湖へ逃げ出し、琵琶湖全域に広がったと言われて
います。その後、イケチョウガイの寄主は別の魚にとって変わられ、ブルー
ギルは忘れられた存在となっていったのです。
やがて月日が流れ、イケチョウガイは減少の一途をたどり、ブルーギルは
琵琶湖の固有種に悪影響を与えてしまうほど増殖、再び脚光を浴びるように
なりました。現在、ブラックバスとともにブルーギルの駆除対策が行われて
います。
ちなみに、ブルーギルの名前の由来はそのえらぶたにある青黒色斑点から
きており、フランス語では「道化役者」と呼ばれるそうです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
アクア琵琶メールニュースは隔週月曜日に発行しています。
次回の発行は9/10(月)発行予定
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
水のめぐみ館「アクア琵琶」
〒520-2279 滋賀県大津市黒津四丁目2番2号
TEL.077-546-7348 御意見・御要望をお寄せ下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~