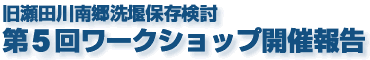●安全の確保と利用は別であり、費用がかかることに関して国交省がどのように考えているかが重要
(⇒旧洗堰を保存するという点について国交省としても同じ思い。当然長期的には保存するための手段を考えるべきだと思っている。ただ、予算等の関係もあり、すべてをすぐにというわけにはいかないことをご理解いただきたい。)
●今のところは、一時利用という事で良いのではないか
・イベント時のみ開放すればよい
・整備が出来れば(将来的に)常時利用すれば良いのではないか
・最終目標を常時開放としつつ段階的に出来る事を行っていけばよい
・緊急にやらなければならない事をまず行う事が大切
・文化財として残すために必要な補強を考えれば良いのではないか
・開放するための補強なのか、洗堰を保存するための補強なのか
・洗堰を未来永劫残すのであれば、耐震補強もしなければならない
・常時開放の工事はお金がかかりすぎるのではないか
・大きな工事が出来ないのであれば、常時利用は出来ない
・補強工事の予算は可能なのかどうか
など |