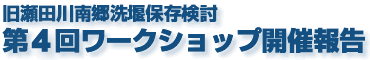|
|
 |
| |
�@
�����P�W�N�V���Q�W���i���j�Ɂu�����c��싽�ۑ�������4�[�N�V���b�v�v���J�Â���܂����B���̃��[�N�V���b�v�́A���j�I�E�����I���l��L���鋌���c��싽�̉��l��F�����A�㐢�Ɏp�����߂̕ۑ����@�⍡��̗����p�̕��@�ɂ��āA�Z���݂̂Ȃ���ƂƂ��ɍl���Ă������Ƃ�����g�݂ł��B��4��̃��[�N�V���b�v�͐V���ȃ����o�[�������A����܂ł̌����̗���ƁA�lj��̃A�C�f�A�o���A���f�����s�Ɍ��������g�݂ɂ��ċc�_���܂����B
�Q���҂̊F�l��肢�������܂����l�X�Ȃ��ӌ����A�����̃��[�N�V���b�v�̗l�q�ƂƂ��ɂ������Ă��������܂��B |
|
| ����l�[�N�V���b�v�̊T�v |
 |
������ |
����18�N7��28��(��) |
| |
����� |
�E�H�[�^�[�X�e�[�V�������i�i�A�N�A���i���j |
| |
����ʎQ���� |
16�� |
| |
���A�h�o�C�U�[ |
���c�@�����i�ߋE��w���H�w���@�u�t�j
�c���@���l�i�F�{��w��w�@�@�������j |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| �P�@���[�N�V���b�v�̎�| |
| �V���ɉ�����������o�[�̊F����ƁA��N�x����p�����ĎQ�����Ă��郁���o�[�̊F����ɁA�Ȃ����싽��Ώۂɂ��ċc�_����̂��H�Ȃ��A����Z���𒆐S�Ƃ������[�N�V���b�v�ŋc�_����̂��ɂ��Đ������s���܂����B |
 |
|
|
 |
| �Q�@����܂Łi�����P�V�N�x�j�̌����ƍ��N�x�̎��g�� |
�V���ɉ�����������o�[�̊F����ɂ͍�N�x�̌����̌o�܂�m���Ă��炤���߂ɁA��N�x����p�����ĎQ�����Ă��郁���o�[�̊F����ɂ͐U��Ԃ�����˂āA����܂ł̌����̗����������܂����B
�܂����N�x�̎��g�݂̖ړI�A�i�ߕ����ɂ��Đ������܂����B |
�y��N�x�̌����̂Ȃ���z |
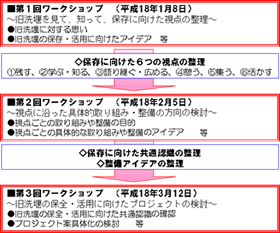
|
|
|
 |
�R�@�ۑ��E�����p�Ɍ������A�C�f�A���� |
�R�O���[�v�ɕ�����āA�u���̕ۑ��E�����p�ɑ���V���ȃA�C�f�A�v�A�u���f�����s�ł���Ă݂������g�݁v�ɂ��ċc�_���܂����B�c�_�͑�Q�[�N�V���b�v�ŗp�����U�̎��_����ɂ��čs���܂����B |
���f�����s�Ƃ́F
�ۑ��E�����p�̃A�C�f�A�̈ꕔ�i���ł��邱�Ɓj�����ۂɎ��s���Ă݂邱�ƁB���ۂɂ���Ă݂邱�ƂŁA�����I�ȉۑ�𖾂炩�ɂ�����A�V�����A�C�f�A���o�����肷�邱�Ƃ�ڎw�����́B |
|
| �y�U�̎��_�z |
���_
�i�L�[���[�h) |
���@�@�@�e |
| �@�c�� |
�����̂₻�̗��j�Ȃǂ��g�c���Ă����h |
| �A�w�ԁE�m�� |
���̉��l����j���A�l�X�Ȑl���g�w�сE�m��h |
| �B���p���E�L�߂� |
���̉��l����j���A������ցg���p���h�A�l�X�Ȑl�ցg�L�߁E���m����h |
| �C�e�� |
�g�e���h�̋�ԂƂ��Ă̖��͂����߂� |
| �D�W�� |
�g�W���h�̋�ԂƂ��Ă̖��͂����߂� |
| �E������ |
�ό��ȂǁA�l�X�Ɂg���p����h��ԂƂ��� |
|
|
|
 |
�S�@�������� |
| �@
�R�O���[�v�ɕ�����āA�c�_�������ʂ��Љ�܂��B |
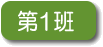 |
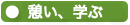 |
�����`����R�̎��_��܂ł̎U���H�̊J��ƁA�����ӂ̃T�C�N�����O���[�h�Ƃ�
�@ �A�g�Ȃǂ��l����B<<�D��xNo1>>
- ����R�ɓo��ƁA���i�`���`���c�쉺���ƁA���̎��ӂ���]���邱�Ƃ��ł���B
����R�́A����]�ށA���ɑ�Ȏ��_��ł͂Ȃ����B
- ����R�̎��_������݉����邽�߂ɂ��A��Ȏ��g�݁B
|
  |
����蕔�ɂ���ċ��̗��j��`����<<�D��xNo3>>
- ���{�̂̂��Ƃ����ł͂Ȃ��A���݂Ɍg������l�X�̋�J�A�p���Ƃ��̑�����s����
�l�X�̋�J�A�����ӂ̕�炵��Y�Ɓi�_�ƂȂǁj�Ȃǂ̕ϑJ�ɂ��Ă��`���Ă���
�K�v������B
- ���͂œ`���邾���ł͂Ȃ��A�u��蕔�v�ɂ���Ęb���Ă�������ق����A���S�ɋ����̂ł͂Ȃ����B
�܂��A�S�ې}�@��n���w�Ƃ��������g�݂��Q�l�ɂ��āA���ɂ܂����j���G����N�\�A
�}�b�v�`���A����ɉf���Ȃǂɂ����܂Ƃ߂邱�ƂŁA��葽���̐l�ɊS�������Ă��炦���
�ł͂Ȃ����B
- �n���␅�Ӌ��c��ȂǂƘA�g��}���Ă������Ƃ���B
���R�P���Ƃ��ȂǁA���̐��|���s���u���v�����{<<�D��xNo2 >>
- ���ɐG���C�x���g�B
- �����̓��{���i�d�v�������j�ł́A���N�ď�Ɂu���v�̃C�x���g�����{����A�����̐l��
�S���W�߂Ă���B
������PR����<<�D��xNo5>>
- ���ɐG���C�x���g�B�S���ߑ㉻��Y�A�����c����{����u�ߑ㉻��Y��Č��J�v��
���킹�Č��J���ƂȂǂ����{���A�p���t���b�g�ɏ����f�ڂ��Ă��炢�A�S���ɍL��PR�B
|
 |
�����̓P�����ꂽ�����K��p���Ƃ��̊p�ނ�T���o���i�������݂��P���𐿂��������炵���c�j�A
�@�W�����Ă͂ǂ����B
�����̈ꕔ�i1�X�p���j������āA����Ɏ����W�����Ă͂ǂ����B |
 |
�i�Čf�j�����`����R�̎��_��܂ł̎U���H�̊J��ƁA�����ӂ̃T�C�N�����O���[�h�Ƃ̘A�g�Ȃǂ��l����B<<�D��xNo1>>
- ����R�ɓo��ƁA���i�`���`���c�쉺���ƁA���̎��ӂ���]���邱�Ƃ��ł���B����R�́A����]�ށA���ɑ�Ȏ��_��ł͂Ȃ����B
- ����R�̎��_������݉����邽�߂ɂ��A��Ȏ��g�݁B
|
 |
���i�Čf�j���̓P�����ꂽ�����K��p���Ƃ��̊p�ނ�T���o���i�������݂��P���𐿂��������炵���c�j�A�W�����Ă͂ǂ����B
���i�Čf�j���̈ꕔ�i1�X�p���j������āA����Ɏ����W�����Ă͂ǂ����B
��������̖͌^��W��������A�p���Ƃ��̊p�ނ�W�������肵�Ă͂ǂ����B
�����炩�̕��@�ŋ��̍��E���݂��q���ŁA���Ă̎p���Č����Ă݂����B
����D���ׂāA�W���Y�R���T�[�g��\����Ȃǂ̃C�x���g��s�������B<<�D��xNo4>> |
|
|
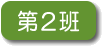 |
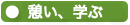 |
���n��̐l���W�܂��Ēn��̂��݂₰�E���Y�Ȃǂ�
�i�l�ɗ��Ă�����Ă����ɉ����Ȃ��̂̓_���j
��������������i�e���������߂�j���ɂ��A��ɐG���@���݂��A
�@
��̑厖�����w��ł��炢�Ȃ���̑厖����`����B
���������Ԃ��̏�ɗ��܂��Ă��炦��悤�ɂ���B�i���y�Y�A�i���X�A
�H�ו��k�̂���̒n��̐H�ו��A�i�m�n�i�Ђ��A�z�^���K�V�Ȃǁl�Ȃǁj�B
���V�����Ȃǂ��ꂢ�Ȃ��̂������莩�R�E����̒��Ő������o����悤�ɂ���B
�����E�������E�Ă�����Ȃǎ��ӎ����Ƃ��킹�Ď��V�ł���悤�ɂ���B |
  |
�����p���A�L�߂邪�d�v�B
����蕔�v���W�F�N�g���s���B
- �u�s�[���v�̌Ăі��A�u�����݂Ƃ�̋L���v�Ȃǂ�`����B
- ���R�Ƃ̐킢�̗��j��A���Ă̎��ӏZ���̑z���A�L�Ƃ�␅�V�тȂǁA
��Ƌ������Ă����̂̂������Ȃǂ�`����B
- �̂̐l�̑z����`����B
- �n��̑z�������������Ƃ������Ƃ���������`����B
���S���������遁�o�q���d�v�B�Ƃ肠�����A�s�[�����ׂ��B�܂��A�l�ɗ��Ă��炤���Ƃ���B
���ē��W���̐ݒu�E�Ŕ̐ݒu�i�������A�Ŕ��̂��݂���j�B
���̃��C�g�A�b�v�i��m�点��j�B
���j�ՂƂ��Ēn�ʂ����߂�B
���p���t���b�g��n���̂ɒu���B
���ό��ŗ����l�ɐ�m���Ă��炤���߁A���c��N���[�Y��싽�܂ŗ��Ă��炤�B
���ߑ㕶����Y�̓��ɑS���ɐ���������B
�����s�s�̓y�؎����ƈꏏ�ɂȂ��Ăo�q����i���̎�����m�邱�Ƃ��d�v�j�B |
 |
���p���Ƃ������ۂɑ̌��B
���������c���B
���p���t���b�g���쐬���Ăo�q���s���B�l���W�܂鏊�ȂǂɃp���t���b�g��u���B |
 |
���D��߂��܂ʼn^�s���A�삩�猩�Ă��炤�i���c��N���[�Y�������܂ł܂킷�j�B |
 |
���u�̂̕��i�Â���v����B
�����E�������E����������C�g�A�b�v����B
���y���݂̏ꏊ�Ƃ��āA��ɐG���悤�Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ����B
���i�����������Ȃ����j���Ē��F�ŊL�Ƃ�����Ă����悤�ɐ�ɐG��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ������B
�����Ă����݂��܂����肵�����A���ł��邱�ƂŐ�ɐe���߂邱�Ƃ��s���B
�������݂ȂǁA���Ă̐H���W�߂�i�����ݕۑ�����݂���j�B
���p�ނȂǂ̎�����̊�����B
- ������̖͌^������āA�݂�Ȃɂ�����Ă��炤�B
- �p���Ƃ��̊p�ނ��x���`�ɂ���B
���Z���ƍs���̖������S���d�v�B�������S�����ꂼ��̐ӔC�m�ɂ��邱�ƁB
- �S�~�Ђ낢�̃{�����e�B�A�̃P�A���s���B�i�s���͊����̃T�|�[�g���K�v�j
- �j�ƂȂ�c�̂����̌������߂ɂ͎Љ�I�n�ʂ��K�v�B
���C�x���g�E�o�q���s���āA�܂������^��ł��炤 |
�����f�����s�S�̂ɂ��ā�
�����f���͂U�̎��_����P���I�����A���f�����s���s���ẮB
�i���ׂĂ̎��_��ԗ����ׂ��j
�����f�����s�͈���ł͂Ȃ�1�T�Ԃ��炢�͕K�v�ł́B |
|
|
|
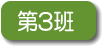 |
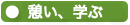 |
���p�����̌����s���B
- ���̂܂��ɖ�������āA���ʂ̍��������邱�Ƃ����������B
- �p�����̊p�ނǂ�ȏd�����m�肽���B
- �p�����̍�Ƃ��ǂ�ȋ�J�Ȃ̂���m�肽���B
�����ɗ����ꂽ�p���Ƃ��̊p�ނ��ǂ����̌����̌��ނɎg���Ă��邩������Ȃ��H
�i�ւ̒Â̏Z��Ŏg�p����Ă��邩���j
�����݂̉����Ȃ��A�����Ă킽���݂苴��������B�i�V�̕��������܂��j |
  |
����蕔���s���B
- �q�ǂ��ɓ`���Ă����B
- ���w�Z�Ō�蕔�����ƁA���z���������̂����A���z����ǂݕԂ����ƂŁA
�`���邱�Ƃ̑厖���A�`����ׂ��|�C���g���ĔF����������B�ˌ�邱�Ƃ�
�����厖�Ȃ̂����t�ɒm�邱�Ƃ��ł���B
- �n��̌Íl�ɂ��b�����@����Ă���ǂ��B
���l�X�ȃe�[�}�ŃK�C�h���s���B
- �ό��D�Ől�ɓ`����B��蕔�K�C�h�AWS�����o�[�̈�l���S������s���Ă���ˍ��ł��邱�ƁI
- �S���������D�ŃK�C�h�B�P���Ԕ��̊Ԃɋ��A��^���ˎ����̗��j�Ƙb���Ă���B
- �D��Ŏ����B
- ���j���e�[�}�ɃK�C�h���s���B
- �s��̎��ォ�璷�����j��m��A�`����
|
 |
�����j�ׂĎc���������邤���Ɏc���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�����j�ׂ�ˍ��q�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�i������x�̂��͎̂��Ԃ��������ɍ�鎖���ł���B�j
- �n��̌ØV�ɂ��b���A���j���q�ɂ���B
- ��l���m�肽���B�n����j�N���u�ɂ������Ăق����B���������͎̂q�ǂ���������Ȃ��B
- �ΎR���̎����͂������邪�A���ӂ̎����͂��܂�Ȃ��B
- ���݂��錾���`���̂��c���Ă����˂��܂�m���Ă��Ȃ��̂�����B
- �̂̉��̗l�q���̂����̂Ɂ�R�Q�̑�@�Ƃ����̎�������B
|
 |
���ό����[�g�Ɏ�荞�ށB
- ���c��̐쉈���i���ɍ��݁j�����]�Ԃ�k���ȂǂŎU��ł���悤�Ȑ��������ꂽ�B
�U���H���ł��A���łɐF�X�ȃO���[�v���������Ă���B
- �쐬�������T�C�N�����O�}�b�v�ɂ����ڂ��Ă���B
|
 |
���̑傫�������ۂɑ̊�����B
- �����ق̂悤�ɃK���X����ʼn������͂݁A���܂ł݂���悤�ɂ���˖{���̑傫�������̌��ł���B
- �K���X����ɂ�����p�ނ���ꂽ���ɂǂ��Ȃ�̂�������B
- �p�ނ��ǂ��܂œ����āA�ǂ̂悤�ɂ��Ď~�܂�̂�
|
���ۑ��E���p�̃e�[�}�ɂ��ā�
���Ƃ����\���������łȂ��A���ӂ̐������A���Ƃ��������_�ōl���Ă݂邱�Ƃ��K�v���Ǝv���B |
|
|
|
|
|
 |
�T�@�������i�Ɣ��\�̗l�q |
| �@
�������̉��̗l�q�Ɣ��\�̗l�q���Љ�܂��B |
 |
 |
�������̉�� |
�������e�̔��\ |
|
|
 |
�U�@�A�h�o�C�U�[����̃R�����g |
�@�A�h�o�C�U�[�̐搶������A����̃��[�N�V���b�v�ɂ��ăR�����g�����������܂����B |
�o�q�����邱�Ƃ͂ƂĂ�������A�`�����X���Ȃ��Ƃo�q���ł��Ȃ��BPR�̕��@�Ƃ��āA�ߑ㉻��Y�̑S����Č��J�ɋ����c��싽���ڂ���Ƃ������Ƃ����肦��B�܂��A�����ّ�w���ÃL�����p�X�œy�؊w��̑S����9/20�`22���ɂ����ĊJ�Â���邪�A���x���Ƃ��ēy�؈�Y���Ɋւ�������Ă̒��ŁA�������̌��Ƃ��ďオ���Ă���A�����PR�̐�D�̋@��ł���
�q�������A�K���l�����ɗǂ����ǂ��`���邩���d�v�ȉۑ�ŁA�n��̏��w���ɗ��Ă�����āA100�N�̗��j�������邱�ƂŊ����Ăق����B���������Ӗ��ł́A�S�N�O�̃����K�����Ēm�邱�Ƃ��ł���悤�Ȏd�|���A���g�݂���悵�Ăق����B�Ⴆ�A���R�Ȕ��z�ŁA�Ȃ��Ȃ����̂̐̕��i������悤�Ɍ�����d�|���ȂǁB�������������g�݂��������āA���������������10�N�A20�N�Ƒ����悤�ɁA�����ɂ��郁���o�[���y�����Ǝv�����ƂɎ��g�ނ��Ƃ�����Ǝv���B |
|
 |
 |
���c�����搶 |
�c�����l�搶 |
|
|
 |
�V�@�ӂ肩����V�[�g�̂��ӌ� |
| �@�Q���҂̊F����ɂ����������A����̃��[�N�V���b�v�̊��z�Ȃǂ��Љ�܂��B |
�C�t�������Ƌ���������
|
| �E�Q���҂̊F����̊S�̍����ɂт����肵���B |
| �E�n���ɂ͋��̎v���o�����A�M���l�����鎖���������B |
| �E���̍H���̓�����ċ������B |
| �E���N��̃����o�[�������̂ŁA�l���E�ӌ��������ł���A�܂Ƃ܂��Ă����B |
| �E�u�Ă�����v�u�������v�����邱�ƁB |
| �E�������������������A�̓��̂��b�������������Ƃ��ł��A�Q�l�ɂȂ����B��ϋ����[���A�����Ƃ����ƂƂ����C�����B |
| �E�u�싽�v�̖��̂��A���P�[�g�ő����������ɋ������B |
| �E�n���̕��̎Q���ɂ��A�܂�������b�����������ƁB�i�Â�����`���̂����铙�j |
| �E4�������Ԋۂɏ���Č�蕔�����s����Ă���l�������B |
| �E�����Ȕ����A���\�ł悩�����B���̕ۑ������łȂ��A�����o�[�͂��̎��ӂ̗��j�I�ȑ��Ղ��Ȃ�Ƃ����̐���Ɍ����ł䂫�����Ƃ����v��������悤���B |
| �E�P�`�R��ł��������ӌ����o�Ă���悤�Ȃ̂ŁA���������Ⴄ�p�x����l���Ă݂����B |
| �E�������Ȃ����̂悤�Ȑ����������B |
| �E���������̘b�͏o���悤�ŁA���Ƃ͎��s����̂݁B |
|
���f�����s�ł�肽������ |
�E����R�̊��p�����ЂƂ������������B�i����o���Ă݂����j |
�E�����̐��|�������������B
|
| �E�S�ې}�@�ŁA�Ⴂ�l����V�l�܂ŃA�s�[������B |
| �E���ӎU��ŁA���ɑ���R�R�����[�g�ւ̒T���ƒ����̎��{�B |
| �E��D��ł̃C�x���g�J�ÁB |
| �E�ߑ㕶����Y�̓��i10/20�j�̎��Ƃ�o�^���B |
| �E�o�q�A���݂ɋ��S�i�ʐ^���̊Ŕ̐ݒu�A���C�g�A�b�v�B |
| �E��Ԋۂ�܂ʼn��ƁB���c��i�ΎR�`�j�S�������悤�Ȃ��ƁB |
| �E�����̂ڂ�𗼊݂���n�������[�v�ɂ邵�ĉj������B |
| �E�q�������ɂ����s�ψ��ɓ����Ă��炢�A�G�߂̗ǂ������ɃC�x���g�����{�B |
| �E���̓����i�A�N�A�r�����j�̈�R�}���K���X����ɂ��Ė��ł����݁A�����đ����̃K���X��茩�ʂ������āA�p�ށi�P�^�j�̏㉺���@�B�I�ɓ��삵�Č��鎖���������B |
| �E���j���q���쐬�B�i�݂̂Ȃ炸�A�̂���̎����̗��j���܂߂����e�Ƃ������B�j |
| �E�L�u�ɂ��A��蕔�A�K�C�h�Ȃǂ̎��{�i���w�Z���ʂ̕��X��ΏۂɁA���j�Ȃǂ�b���B�j |
| �E�G�R�c�A�[�̊J�ÁB |
|
�����E�����Ȃ� |
�E���j�̕��B�i��蕔���璮�����@�j
|
| �E�n���Z���łȂ��̂ŋ��ւ̎v���͗]��傫���Ȃ��A�����Ƃ��̒n��S�ʂɓn���ĊJ���E���p�̂��߂ɗ͂����W�������B |
| �E���|�Ȃ�A�������ł��Ⴂ���ł��C���Ăق����B |
| �E���A�l�^�A�n���Z���������̂ŁA�m�b�̎g�����Ō㐢�Ɏc��A���_�ɂȂ�\��������̂ł�肪����������B |
| �E���낢��ȏ��Ŗ��ɗ��������B |
| �E�Ŕ��グ�āA�o�܁E�ړI�����f����B�f�����{�^���������Ό�����悤�ɁA�Ŕ̓��e���f���Ō�����B |
| �E�q�������ɓ`���A�q�������Ƌ��ɍl����B |
| �E���a11�N�Ȍ�A���݂܂ł̏o�����������`��������������B |
| �E�܂��A���ӗ��j���L�������q�Â���Ɏ��g�݂����B |
| �E���[�N�V���b�v�����o�[�̑��ɂ��u���i�Η��j��y���v�Ƃ������D����̃E�H�[�^�[�X�e�[�V���������_��2�������Ƃɔ��\������Ă���i���������o�[�̈�l�j�B���̓��D��ɂ��Ăт����ďڂ������������A���q�Â�������Ă͂ǂ����Ǝv���B����ƕ��s���āA���ӗ��j�̉���i�b�j������̂��悢�B |
| �E���������l�������Ăق����B |
|
| ���̑����z |
�E���E���w���ɊS�������ĎQ�悵�Ă��炢�����B
|
| �E���܂�c�_�Ɏ��Ԃ��₷�̂ł͂Ȃ��A��̓I�Ȋ����ɗ͂���������������Ǝv���܂��B |
| �E����Ɏ�����̖͌^��̂��悢�ȂƎv�����B |
| �E�S�N�̕i�����c���Ƃ������Ƃ͑�ςȍ�ƂɂȂ�̂��Ɗ������B |
| �E��4�J�Â��ꂽ���Ɋ��ӂ��Ă��� |
| �E�q���ɂ͒n��w�K���Ő��w���Ăق����B |
| �E7���̏W�����J�ɂ���āA�싽�̉ʂ����Ă����ڂ�ڂ̓�����ɂ��A
��l�̈̋Ƃ�[���������B |
|
|
|