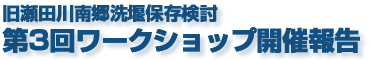|
| ・新洗堰の働き(水との闘いの様子)を見て学び、旧洗堰の果たして来た役割や歴史を学んでいくことが効果的ではないか。 |
 |
| ・角落しの体験イベントを開催したり、角落しの角材を使ったベンチを設置したり、触れて学ぶ工夫も大切である。 |
| ・見て学ぶ、触れて学ぶ拠点として、旧洗堰左岸下流側のテラスや新洗堰右岸下流側の橋詰に、説明サインや角落しの角材を使ったベンチを設置することが考えられる。 |
 |
 |
| ・イベントにあわせて、左岸側の旧洗堰周囲に台船(仮設)を設置したり、旧洗堰左岸上流側に川床を張り出したりして、能やジャズコンサートの開催、オープンカフェの設置などを行っても良い。ただし、台船や川床の設置はイベント時の仮設として、普段は景観を阻害しないようにする。 |
 |
|
| ・右岸側バス停を、壁が無い開放的であずまや風のものに作り変え、南郷の玄関口として人が憩える空間(休憩所)、観光案内所を兼ねたスペースとして活用する。 |
|
| ・バス停に案内板を併設。案内板は現在あるものより内容の充実が必要。(南郷地域の観光施設が一目でわかるマップ、左岸側(アクア琵琶などの施設)についての紹介、旧洗堰建設に至った経緯(洪水の歴史、治水の歴史)や新洗堰の役割などを小・中学生にも分かりやすく写真やイラストを交えてビジュアル的に表現したものなど) |
|
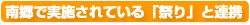 |
 |
| ・毎年5月に開催される「船幸祭」、7月末に開催される「南郷公園夏祭り」と連携させた洗堰をテーマにしたイベントを開催。 |
| ・5月には旧洗堰の両岸にかかる「航行禁止」のロープに鯉のぼりを並べてみてはどうか |
 |
| ・連歌の美しい旧洗堰の下流側を“表”、上流側を“裏”として、“表”はライトアップされた堰そのものを、“裏”は間からこぼれる光が生み出す旧洗堰のシルエットの美しさを、新洗堰や上流方向右岸側から鑑賞する。 |
 |
 |
| ・旧洗堰の管理橋の上に、少し嵩上げした舞台を設置すれば、その上で演奏等が行える。 |
| ・上流側は、仮設ベンチや堤防を階段状の河川構造物として整備することなどで、観客席を設けることができるのでは。 |
 |
|
| ・「建設当時の状態を復元しレンガ色を再現すること」と「時を経てきた歴史を大切にするため、汚れ(コケなど)を落とさず、今の状態で残す」こと、双方大切。 |
|