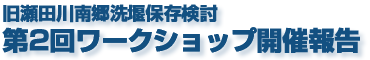| 2.学ぶ・知る 4.憩う(あわせて議論) |
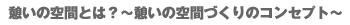 |
 |
・
旧洗堰の周辺空間が憩いの空間として親しまれ続けるためには、地域住民や来訪者に日常的に使いこなされていることが大切である。 |
 |
| ・
そのためには、まず、自分たち(ワークショップメンバー)が楽しめる空間であることが大切である。 |
| |
・
その楽しさを周囲の人々や来訪者と共有したいという思いが、洗堰とその周辺の歴史を学び、知る、そして伝える動機となる。 |
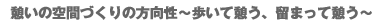 |
| <歩いて憩う> |
| |
・
歩いて憩うことを楽しむことが大切である。 |
| |
・
歩いて憩いながら、旧洗堰の歴史や役割を学ぶ工夫をちりばめることで、学びの空間としても親しまれると考えられる。 |
| <留まって憩う> |
| |
・
ゆったりとコーヒーを飲みながらくつろいだり、景観を楽しみながら物思いにふけったり、留まって憩うことのできる空間づくりが大切である。 |
| |
・
水面からの旧洗堰の眺め、大日山からの眺望など、新たな視点場の発掘が旧洗堰周辺の魅力をさらに高めると考えられる。 |
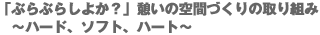 |
| <ハード> |
| |
・
上流側・下流側」を繋ぐ遊歩道を整える。各視点場近傍を使いやすい場として整える。 |
| |
・
左岸側の旧洗堰の堰上を開放して、旧洗堰に直に触れられるようにする |
|
| |
・
角落しの角材を復元して実際に触れられるようにしたり、旧洗堰のそばに説明コーナー/説明サインを設けたりするなど、学びの工夫をちりばめる など |
|
| <ソフト> |
| |
・
周辺の遊歩道や使える空間(視点場、溜まり場)の情報を広く発信し、多くの人に使ってもらえるように工夫する |
|
| |
・
空間の使い方(楽しみ方)を公募する(視点場近傍のオープンカフェや台船を使ったイベントなど) |
|
| |
・
アクア琵琶の展示と説明コーナー/説明サイン、休憩所の展示との連携を図る など |
|
| <ハート>
(プロジェクトを動かす、第一歩を踏み出す人づくり) |
| |
・
ワークショップメンバーが旧洗堰周辺で憩い、楽しむことを目的として、旧洗堰周辺の良さを知り、その良さを周囲の人々や来訪者に伝える企画を実施する(ウォークラリーのワークショップメンバー版) |
|