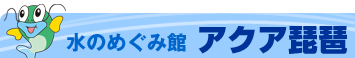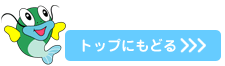治水の歴史
琵琶湖の洪水を予防するためには、唯一の出口である瀬田川を浚渫(しゅんせつ)(川底の土砂さらい)し、水の流れを良くしてやることが最も効果的です。しかし、瀬田川の疎通能力(流れる水量)が大幅にアップすると、洪水時には下流の淀川に多量の水が流れ出て危険な状態になる一方、渇水時には湖水位が低下する原因にもなります。瀬田川洗堰は、琵琶湖と淀川の両方の洪水を調整して水量を一定に保つ、いわば洪水予防の番人なのです。
奈良時代〜江戸時代
行基(ぎょうき)の瀬田川開削(かいさく)計画

大日如来がまつられている大日堂

大日如来
奈良時代の僧・行基は、琵琶湖の洪水を防ぐには瀬田川を開削して湖水の流れを良くするしかないと考え、川中に飛び出た大日山を切り取ろうとしました。しかし、それによって下流に氾濫が起こることを恐れ、工事を断念しました。その際行基は山頂に大日如来をまつり、今後この山を切り取ろうとすればたたりがあるとの言い伝えを残したため、明治になるまで大日山に手につけるものはいませんでした。
藤本太郎兵衛親子の活躍
高嶋郡深溝村の庄屋、藤本太郎兵衛の親子3代にわたる努力によって、自普請(じふしん)による本格的な川ざらえが実現しました。
河村瑞賢(かわむらずいけん)の大普請(だいふしん)
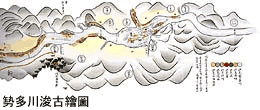
江戸時代、洪水に悩む湖周辺の人々が、幕府に何度も瀬田川の川浚えを嘆願した結果、数度の普請(工事)が実現しました。そのうち元禄12年(1699)の普請では、河村瑞賢が工事の指揮をとりました。瑞賢は現在の瀬田橋から旧洗堰までの東岸を切り取るとともに、黒津八島の洲を崩して2つの島とし、通水を良くしました。工費は幕府が一時立て替えた後、周辺の村々に3年の年賦(ねんぷ)で割り当てられました。
明治・大正時代
大越亨(おおごし とおる)知事の活躍

大越知事の功に対して建てられた記念碑(石山寺境内)
瀬田川改修の重要性を見抜いた大越亨知事は、浚渫工事を内務省に上申しました。流域府県とも交渉を重ねた結果、明治26年、部分的に工事が実現しました。
大日山の切り取り
明治34年(1901)、奈良時代に行基が断念して以来、手つかずだった大日山が初めて切り取られ、瀬田川の流れが増大します。
南郷洗堰(旧洗堰)の築造
中井弘知事が堰の必要性を説き、明治38年に完成。堰はレンガ造りで、開閉は人力だったが当時としては画期的。
近代の治水事業
瀬田川洗堰(新洗堰)の築造
昭和36年、瀬田川改修計画の一環として、新洗堰が完成。自動操作のため、操作時間は大幅に短縮。水量を正確に放流することが可能となった。
琵琶湖総合開発事業の終結
昭和48年(1973)、湖周辺などの洪水被害を解消するための治水、琵琶湖の自然環境を守るための保全、琵琶湖の有効利用をはかるための利水を3本の柱に、国・県・市町村・水資源開発公団などが25年間もの歳月をかけ一丸となって実施されました。そして、平成9年(1997)8月7日に終結しました。