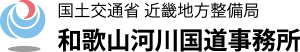紀の川の歴史history-kinokawa
和歌山は、紀伊山地の雄大な山並みをはじめ、大小多数の河川や、黒潮に洗われた海岸線など美しい自然に恵まれています。歴史的資源も数多く残されており、地域ごとの個性も多彩です。
古代には国府が置かれ、江戸時代には紀州徳川家の城下町としてにぎわった和歌山。大和朝廷時代には都と和歌山を結ぶ街道がつくられ、時代ごとに役割を変えながら発展していきました。また、紀の川の水運を利用して古くから国内外との交流が盛んで、紀伊山地は神々が鎮まる特別な地として全国から多くの人が訪れ、山岳霊場に至る参詣道が誕生しました。
紀州にゆかりのある人物
有吉佐和子(1931~1984)
小説家。ルポルタージュや演劇の脚本・演出などの分野でも幅広く活躍した人物。和歌山市真砂丁(現・吹上一丁目)生まれ。銀行員であった父の転勤に伴い、小学生時代をインドネシアと日本で過ごす。敗戦直前に帰国し東京に住むが、昭和20年の東京大空襲によって、静岡を経て和歌山に疎開する。昭和24年には東京女子大学文学部に入学。以後、同大の短大に進学し、歌舞伎研究会に所属する。この頃から文筆活動を開始し、昭和31年には『地唄』が芥川賞の候補となる。それ以降も『紀ノ川』『助左衛門四代記』『有田川』『日高川』『華岡青洲の妻』など、ふるさと和歌山を題材とした作品を次々と発表。これらの作品の登場人物はしなやかな紀州弁を話し、戦後小説に新たな価値観を生んだとして、高い評価を受けている。その後も『恍惚の人』や『複合汚染』などの社会派作品を発表した有吉佐和子は、昭和59年に53歳という若さながら急性心不全で不帰の人となった。

松下幸之助(1894~1989)
実業家であり、松下電器産業の創立者。和歌山県和佐村に8人兄弟の末っ子として生まれる。父が相場で失敗したことで、小学校を中退して大阪へと丁稚奉公に出る。そこ時、子守りなどをしながら店を手伝うことで、商売人としての心得を修得する。また、この頃よりお金を活かして使う才能の片鱗を見せ始める。その後、自転車店やセメント工場に勤務し、これからは電気の時代であることを見抜き大阪電灯に入社。さらに22歳の時には独立して、妻と義弟とで作った電球ソケットの販売を開始する。当初は売れなかったものの徐々に売れ始め、翌年には松下電気器具製作所を設立した。続けてランプやアイロンを商品化し、昭和5年には故障し難いラジオを開発。これが世間に広く認められ、一気に電器メーカーとしての地位を確立した。その後も貿易、造船、飛行機などの関連会社を設立し、アメリカにも進出。世界のパナソニックに成長する。また、松下幸之助は一流の経営者でありながら、一流の思想家でもあった。昭和55年には松下政経塾を開塾。この塾からは多くの政治家を輩出している。

井沢弥惣兵衛(1663~1738)
江戸時代を代表する治水家。名を為永(ためなが)といい、紀伊国那賀郡溝口村に生まれる。紀州藩士であった徳川吉宗の将軍就任後に幕臣となる。1722年に幕府の勘定所に召され、25年には勘定吟味役格、31年に勘定吟味役となり、35年には美濃国の郡代を兼任する。吉宗からの信頼は非常に厚く、享保の改革においても治水や農業開発において、その敏腕を発揮した。河川を中心とする土木技術において、数多くの新機軸を開発。その手法は紀州流の開祖となっている。1728年に完成させた、利根川中流部から取水の見沼代用水(埼玉県)60キロは、武蔵国の農業開発や水運に多大なる貢献を及ぼしたもので、彼にとっての代表的事業と言える。また、木曽川三川分流の宝暦治水も彼の設計である。
陸奥宗光(1844~1897)
幕末・明治期に活躍した政治家。紀州藩重役・伊達千広の子として、現在の和歌山市吹上三丁目に生まれる。1862年に脱藩し、翌年には勝海舟の主宰する海軍塾に入塾。そこで、坂本竜馬と出会い親交を深める。竜馬と行動を共にし、討幕運動にも奔走した。1878年には国事犯で刑務所へと収監されるが、1883年に出獄。その後は外交官として活躍する。1888年にはワシントン在勤を命じられ、メキシコとの日墨修好通商条約の調印に成功。これは、近代日本国家が諸外国と締結した初めての平等条約だった。まさに、平等外交の始まりと言える。帰国後は、第一回総選挙に和歌山一区から出馬し、当選。第二次伊藤内閣では外務大臣として、不平等条約の改定に尽力を注いだ。1894年にはロンドンで日英通商航海条約を調印。これにより、治外法権の撤廃と関税自主権の一部回復が行われる。さらに翌年には、日清戦争講和条約調印全権団として下関に臨み、日本で初めての対外戦争における戦後処理に携わる。この調印後に体調不良となり、1897年8月24日に死去した。
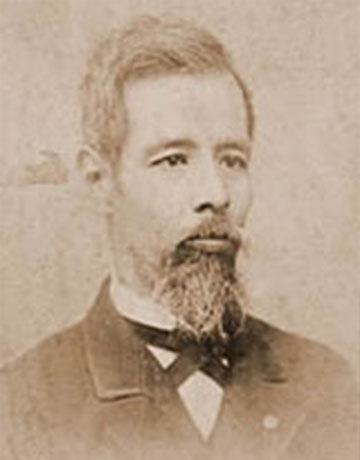
南方熊楠(1867~1941)
植物学や細菌学に留まらず、天文学、民俗学、宗教学にも精通した学者。和歌山城下橋丁で、金物商弥兵衛の次男として生を受ける。小・中学校時代を和歌山で過ごし、上京後、共立学校を経て大学予備門(現・東京大学)に進学。しかし、その能力の高さゆえに学問のレベルが合わず中退。その後、渡米し、シカゴで地衣類学者のカルキンスに師事して標本作成を学ぶ。さらにキューバ、イギリスと渡り、大英博物館で嘱託となりながら、独学で菌類の研究を続ける。この間に科学誌『Nature』に寄稿、帰国後も研究は継続して行われ、計10回の論文が採用されている。また、粘菌だけでなく民俗・歴史・文学等の分野にも論文を発表。その学識の広範さから、博物学者と評される。帰国後からは田辺に居を構えて植物採集に熱中していたが、1906年末に布告された「神社合祀令」によって、植物が絶滅することに憂いを感じ、環境保護運動に立ち上がる。1929年に昭和天皇が和歌山に行幸した際は、求められて進講の役目を果たした。
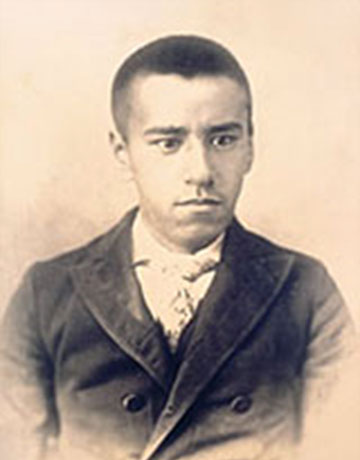
片山哲(1887~1978)
和歌山人初の内閣総理大臣。社会民主主義右派の政治家であり、熱心なクリスチャンでもあった。1887年生まれ。東京帝国大学独法科を卒業後、弁護士となり、法律の民衆化を強く唱えて中央法律相談所を開設。日本労働総同盟、日本農民組合などの顧問も務め、無産者の訴訟に力を尽くした。1926年、社会民主党の創立に伴い、書記長に就任。1930年の第二回普通選挙では神奈川県より出馬し、衆議院議員となる。1932年には社会大衆党の結成に参加。しかし、二年後に日中戦争批判演説を行った民政党・斉藤隆夫代議士の除名に反対したことがきっかけで、社大党を除名される。戦後は日本社会党結成の中心人物となり、書記長に就任した。1974年には社会党首班の三党連立片山内閣を組織。和歌山県人として、初めての内閣総理大臣となる。
前畑秀子(1914~1995)
水泳選手でオリンピックの金メダリスト。結婚後は兵藤秀子となる。和歌山県橋本町生まれ。1932年のロサンゼルス大会の200メートル平泳ぎで、オーストラリアのデニスに敗れて二位になる。これが選手生活で初の敗戦だった。その後、雪辱を果たすべく、4年後のベルリン大会まで毎日2万メートルを泳ぐという過酷な練習を積み、見事に優勝を勝ち取る。決勝レースではドイツのゲネンゲルと息詰まる接戦を演じた。その時、実況中継したNHKアナウンサーが連呼した「前畑がんばれ!」のフレーズはあまりにも有名。1981年にはオリンピック功労賞を日本人女性として初めて受賞した。1983年には水泳教室の指導中に脳出血で倒れるも、1年余りのリハビリ生活を乗り越えて、社会復帰も果たしている。
武蔵坊弁慶(不明~1189)
平安時代末期の僧兵。熊野別当湛増の子供で、紀伊国(現・田辺市)に生まれたとされている。もともとは、比叡山の僧で、五条大橋の決闘以来、源義経に仕えるようになる。歴史的にもミステリーなところが多く、実在したのかどうかを疑われるほど、謎の多い人物でもある。その一方で、『平家物語』を初めとした創作の世界では大活躍が目立ち、義経と並ぶ主役格と言える。また、「弁慶の泣き所」や「弁慶の七つ道具」など、慣用句にも用いられることでも知られる。現在の田辺市役所前には、奥州衣川の戦いで、主君義経を守るために壮絶な死を遂げた弁慶を弔うように、六代目の弁慶松が植えられている。